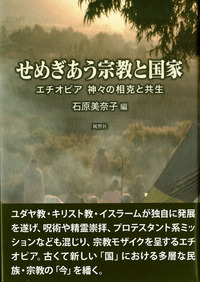目次
●第一部 国家と宗教
第一章 国家を支える宗教──エチオピア正教会(石原美奈子)
一 「失われた聖櫃」のありか──エチオピア独自のキリスト教
二 エチオピアにおけるキリスト教の受容と発展
三 宗教が支配する時間
四 宗教が支配する空間
五 国家とエチオピア正教会
第二章 国家に抗う宗教──イスラーム(石原美奈子)
一 アウリア学校事件
二 エチオピアのムスリム
三 エチオピアにおけるイスラーム導入の歴史
四 EPRDF政権とイスラーム
五 国家とイスラーム
●第二部 遍在する信仰
第三章 邪視・変身・食人──エチオピア・マロにおける呪術的信仰の諸相(藤本 武)
一 エチオピアのブダ──邪視・変身・ゾンビ・食人の世界
二 マロの社会と宗教
三 エチオピアにおける呪術的信仰の特異性
第四章 福因と災因──ボラナ・オロモの宗教概念と実践(田川 玄)
一 ボラナの村落での経験から
二 ボラナ社会について
三 天/神の概念――ワーカ
四 ワーカとの媒介──カッル
五 福因論──繰り返される祈願と祝福
六 災因論──災いの認識と対処
七 ボラナの福因論と災因論
●第三部 精霊と権力装置
第五章 精霊憑依と新たな世界構築の技法──農牧民ホールにおけるアヤナ・カルトの意味世界(宮脇幸生)
一 精霊と出会う
二 エチオピアにおける精霊憑依
三 ホールの伝統と家父長制イデオロギー
四 アヤナ精霊カルト
五 ホールの文化とアヤナの革新
六 抵抗と欲望
七 精霊憑依と新たなアイデンティティの構築
第六章 世俗を生きる霊媒師──カファ地方におけるエコ信仰の盛衰(吉田早悠里)
一 村から消えた精霊と霊媒師
二 エコ信仰
三 カファ地方の歴史におけるエコ信仰
四 変化するエコ信仰
五 変化する社会とアラモ
六 宗教的周縁へ
●第四部 対立と共存
第七章 対立・干渉・無関心──バンナにおける福音主義の布教と共存の振幅をめぐって(増田 研)
一 一九九九年、干魃の年
二 バンナにおけるミッションの活動
三 日曜学校
四 改宗をめぐる葛藤
五 「すべては聖書の中にある」
六 ミッションがもたらしたもの
七 祈り──誰に祈っているのか
八 共存の振幅
第八章 対立を緩和する社会関係──ジンマ農村のムスリムとキリスト教徒(松村圭一郎)
一 隣り合って暮らすムスリムとキリスト教徒
二 「くり返される宗教対立」をめぐって
三 強調/隠蔽される宗教の境界
四 日常的相互行為のなかの宗教
五 宗教の差異に向き合う
●第五部 偏在する神性を求めて
第九章 ショワ・オロモの悩みと対処──エチオピア・ボサト郡周辺の参詣にみられる「共同性」(松波康男)
一 「線」としてのフィールドワーク
二 ボリと複数の参詣地
三 ボサト郡周辺の参詣地の特徴
四 ファラカサ参詣
五 「悩み持ち」の織り成す「共同性」
おわりに
索引
内容説明
ユダヤ教・キリスト教・イスラームが大航海時代以前から受け入れられ、独自に発展を遂げていた国エチオピア。呪術や精霊崇拝、プロテスタント系ミッションなども混じり、宗教モザイクを呈する古くて新しい国家の多層な民族・宗教の関係を繙く。
*********************************************
序より
……このようにいま、エチオピアでは宗教が「熱い」。もっともそれはエチオピアに限ったことではなく、アフリカに広くみられる現象のようである[落合 二〇〇九]。宗教の「熱さ」は、宗教に関連するさまざまな活動が近年、とりわけネオリベラリズムのもとで、活発になってきたことに表れている。さまざまな宗教組織が生まれ、宗教指導者が影響力を発揮し、メディアを駆使して宗教的メッセージを広めている。宗教組織は、特定の宗教的メッセージを広めるだけでなく、医療・教育・貧者救済など福祉活動を展開することで社会的ニッチを獲得し、信者も増やしている。スミスは、構造調整政策導入以降のアフリカ各国では、国家が国民の健康で平和な日常を送りたいという希望や期待に応えることができなくなったことと宗教への期待の高まりを関連付け、宗教が国家の代替機能を果たしていると示唆している[Smith 2012]。
エチオピアにおいても、そうした側面はみられる。エチオピアにおいて「宗教」といった場合、他のサブサハラ・アフリカ諸国と事情が異なるのは、三つのセム系宗教(ユダヤ教・キリスト教・イスラーム)が大航海時代以前に受け入れられ、独自に発展を遂げていた点である。その意味で、エチオピアは宗教的には(サブサハラ・アフリカというより)北アフリカに分類されるべきかもしれない。だが、本書でとりあげる「宗教」は、いわゆる世界宗教(設立宗教)のみならず、在来のアニミズムや呪術、精霊崇拝などを含む広義の「宗教」である。広義の「宗教」は、エチオピアの八〇以上あるとされる諸民族にとって、運命(幸福や災害)を理解したり説明したりするための装置でもあれば、隣接する集団との区別や境界を明確にするための集団認識の媒体でもあれば、またはそれを通して自他の違いを表現・認識する手段でもある。だが「宗教」は、民族のなかでその独自性が完結するのではなく、生活共同体から地域・民族、国家ひいてはグローバルな広がりのなかで重層的にとらえる必要がある。それならばなぜ「エチオピア」という国のしばりにこだわるのか。グローバル化やトランスナショナリズムが現代世界の潮流とされるのに、まるで時代に逆行するかのようにあえて「国家」に注目する意味はなにか。
エチオピアは、アフリカ大陸のなかで特異な国である。近代的な意味での国家の呈をなしたのは、二〇世紀に入ってからであり、その意味では植民地支配を受けてそれをもとに独立後の国家づくりがなされた他のアフリカ諸国と何らかわりはない。ただ、本書の第一章と第二章でとりあげるように、エチオピアは(エチオピア北部〜エリトリアにかけて支配した)アビシニア王国の時代から、一九世紀末の征服によって支配下におく南部諸社会との間に交易・布教活動や征服・貢属などの関係を通して、ゆるやかなまとまりをなしていた。そしてその「まとまり」ゆえに、一定の文化的共通性がみられるのである。レヴィンがその著『大エチオピア』で示しているように、エチオピアは民族・言語的に多様ではあるが、①諸民族同士が相互作用を繰り返してきたこと、②汎エチオピア的な文化的特色があること、③外部からの定期的な侵入に対して特徴的な仕方で反応してきたこと、からゆるやかな統合を形成してきた[Levine 1974: 40]。
狭義の宗教(世界宗教)に視野を限定すると、エチオピアはばらばらなピースからなるパズルにしかみえないが、広義の「宗教」に注目すると、「大エチオピア」の姿が見事に浮かび上がってくるのである。したがって本書は、単に文化人類学者がそれぞれ調査研究の対象としてきた民族における(広義の)「宗教」の実践について報告したものを集めたものではない。個別の民族や集団の「宗教」の実践をみると、歴史的に作り上げられてきた「(大)エチオピア」というゆるやかなまとまりから近代国家としてのエチオピアが生まれてきたことが鮮明に浮かび上がってくるのである。
ただ忘れてはならないのは、この場合のゆるやかな「まとまり」も近代国家も、かならずしも平和的に形成されたものではなく、多分に暴力が介在しながら達成されたことである。征服者/被征服者の間には常に優劣があり、搾取者/被搾取者の関係があった。そして征服者・搾取者はエチオピア北部の高地部をすまいとしてきたセム系(アムハラ・ティグライ)のキリスト教徒であった。そして被征服者・被搾取者はクシ系やナイル・サハラ語族の諸民族で多くが在来の神霊観念をもつか、もしくはムスリムであった。
本書は、『社会化される生態資源──エチオピア 絶え間なき再生』(福井勝義編著、京都大学学術出版会、二〇〇五年)、『抵抗と紛争の史的アプローチ──エチオピア 国民国家の形成過程における集団の生存戦略』(福井勝義編著、二〇〇七年)のいわば「続編」として、宗教に焦点をあてた作品として編まれた。執筆者もかなり重複している。だが前二書は、エチオピア南部の諸民族に関して、一九世紀末〜二〇世紀初めにエチオピア高地部のセム系キリスト教徒と「ファースト・コンタクト」があったことを前提とした論文が大半を占めた。それは「生態資源」あるいは「国民国家」に焦点をあてていたからである。しかし、「宗教」からエチオピアをみた場合、ローカルな論理だけでは説明できない、トランスローカルな側面がむしろ顕著になってくる。「宗教」のトランスローカリティは、宗教的エージェント(宗教組織・宗教指導者・信者・霊媒・精霊など)の移動や戦い・交易などの集団間接触によってもたらされる。「宗教」は、個人や集団の相互行為を通じて、伝染し、模倣され、想像/創造される。「宗教」は共同体の道徳や境界を再確認するためにあるだけではなく、新たな価値観や外来者の代名詞となったり、あるいは個人にとっては共同体の外の生き方の選択肢を与えるものとなったりもする。一方「宗教」は、国家や政治にかかわってくる場合は文字となって記録され、「歴史化」されるが、女性など社会的弱者の「宗教」や日常生活の中での宗教行動などは「書かれる」ことなく等閑視される傾向があった。本書ではそうした「歴史化」された宗教のみならず、「歴史」から漏れ落ち「文字化」されてこなかった「宗教」にも目を向けることによって、エチオピアの宗教の重層性を明らかにしたい。具体的な組織や教義をもった「上からの宗教」だけでなく、日常生活に埋め込まれた「下からの宗教」を人々の思いや行動に即して「文字化」することによってきっと躍動感のある「エチオピアの宗教」を描くことができるに違いない、そのような確信のもとに本書は編集されている。
本書の執筆者の大半は、EPRDF政権成立直後からエチオピア南部で調査研究を推進してきた文化人類学者たちである。いいかえると、ここ二〇年間の対象社会の変化の証人たちでもある。長い現地社会とのつきあいのなかで、執筆者たちはこれまでさまざまな観点からそれぞれの対象社会について書いてきた。したがって今回「宗教」をキーワードにしているが、それぞれの論文の書きぶりや切り口はずいぶん違う。もっともいずれの論者も、それぞれの対象社会で人々の日常の実践のなかに埋め込まれた宗教的観念や行動を人々の視点から説明を試みており、その意味では微視的かつ実証的であるが、同時にそこに描写されている出来事の歴史性や地域的拡がりを視野にいれることも忘れていない点で共通している。……
*********************************************
編者紹介
石原美奈子(いしはら みなこ)
1967年生まれ。
1998年東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。博士(学術)。
専攻は文化人類学、アフリカ地域研究。
現在、南山大学人文学部准教授。
主著書として、『Muslim Ethiopia』(Palgrave、2013年、共著)、『社会変動と宗教の〈再選択〉―ポスト・コロニアル期の人類学的研究』(風響社、2009年、共著)、『社会化される生態資源』(京都大学学術出版会、2005年、共著)など。
執筆者紹介(掲載順)
藤本 武(ふじもと たけし)
1967年生まれ。
1999年京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(人間・環境学)。
専攻は文化人類学、アフリカ地域研究。
現在、富山大学人文学部准教授。
主著書として、『Landscape, Power and Process』(Berghahn、2009年、共著)、『はじまりとしてのフィールドワーク』(昭和堂、2008年、共著)、『社会化される生態資源』(京都大学学術出版会、2005年、共著)、論文として「フロンティアの変容」(『アフリカ研究』80号、2012年)、「アフリカにおける牧畜民・農耕民紛争」(『文化人類学』75巻3号、2010年)など。
田川 玄(たがわ げん)
1965年生まれ。
2000年一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。
専攻は文化人類学、アフリカ地域研究。
現在、広島市立大学国際学部准教授。
主著書として『人と動物、駆け引きの民族誌』(はる書房、2011年、共著)、『セックスの人類学』(春風社、2009年、共著)、『社会化される生態資源』(京都大学学術出版会、2005年、共著)、論文として「『生れる』世代組と『消える』年齢組 : 南部エチオピアのオロモ語系社会ボラナの二つの年齢体系」(『民族学研究』66巻2号、2001年)など。
宮脇幸生(みやわき ゆきお)
1958年生まれ。
1984年京都大学大学院文学研究科修士課程修了(社会学)。博士(人間・環境学)。
専攻は比較社会学、文化人類学。
現在、大阪府立大学人間社会学部教授。
主著書として、『辺境の想像力:エチオピア国家に抗する少数民族ホール』(世界思想社、2006年)、『講座世界の先住民族 ファースト・ピープルズの現在05 サハラ以南アフリカ』(明石書店、2008年、共著)、『社会化される生態資源』(京都大学学術出版会、2005年、共著)、論文として「国家と伝統のはざまで エチオピア西南部クシ系農牧民ホールにおける女子〈割礼〉」(『地域研究』6巻1号、2004年)など。
吉田早悠里(よしだ さゆり)
1982年生まれ。
2011年名古屋大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。博士(文学)。
専攻は文化人類学、マイノリティ研究。
現在、大阪府立大学・日本学術振興会特別研究員。
主な論文として、「被差別マイノリティによる自己表象をめぐる自発的実践:エチオピア南西部カファ社会に生きるマンジョの事例から」(『アフリカ研究』75号、2009年)、Struggle for Social Discrimination: Petitions by the Manjo in the Kafa and Sheka zones, Southwest Ethiopia、(Nilo-Ethiopian Studies、No.18、2013)など。
増田 研(ますだ けん)
1968年生まれ。
1998年東京都立大学大学院社会科学研究科社会人類学専攻博士課程単位取得退学。博士(社会人類学)。
専攻は社会人類学。
現在、長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科、国際健康開発研究科准教授
主著書として、Changing Identifications and Alliances in North-east Africa::Vol. I: Ethiopia and Kenya(Berghahn、2009年、共著)、『社会化される生態資源』(京都大学学術出版会、2005年、共著)、論文として「武装する周辺:エチオピア南部における銃・国家・民族間関係」(『民族學研究』65巻4号、2001年)、「国際保健分野における文化人類学的アプローチ」(『公衆衛生誌』59巻3号、2012年)など。
松村圭一郎(まつむら けいいちろう)
1975年生まれ。
2005年京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。
専攻は文化人類学。
現在、立教大学社会学部准教授。
主著書として、『ブックガイドシリーズ基本の30冊 文化人類学』(人文書院、2011年)、『所有と分配の人類学』(世界思想社、2008年)、『社会化される生態資源』(京都大学学術出版会、2005年、共著)、『現代アフリカ農村と公共圏』(アジア経済研究所、2009年、共著)、論文として「飢餓と森林回復:エチオピア北部の食糧援助にみる『環境』のジレンマ―」(『文化人類学研究』12巻、2011年)、「〈関係〉を可視化する:エチオピア農村社会における共同性のリアリティー」(『文化人類学』73巻4号、2009年)など。
松波康男(まつなみ やすお)
1979年生まれ。
2007年南山大学大学院人間文化研究科博士前期課程修了。修士(人類学)。専攻は人類学。
現在、一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程在学。
主な論文として、「バラカの具現と分配:エチオピア西部ヤア聖者廟村の事例から」(南山大学提出修士論文、2007年)、「異質な参詣者と聖地の共同性:エチオピア・ボサト郡に見られる参詣の諸相」(『年報人類学研究』3号、2013年)など。