
人類学者、台湾映画を観る
魏徳聖三部作『海角七号』・『セデック・バレ』・『KANO』の考察
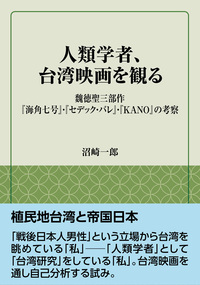
植民地台湾と帝国日本。映画にこめられた歴史や民族のアヤを、戦後日本人男性という立脚点を定めて、さまざまな角度から読み解く。
| 著者 | 沼崎 一郎 著 |
|---|---|
| ジャンル | 人類学 文化遺産・観光・建築 |
| シリーズ | 風響社ブックレット |
| 出版年月日 | 2019/06/10 |
| ISBN | 9784894894037 |
| 判型・ページ数 | A5・86ページ |
| 定価 | 本体800円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
目次
Ⅰ ポストインペリアルという視座
1 「帝国の末裔」であるということ
2 日本におけるポストコロニアリズム受容への疑問
3 割り切れない立場性を引き受ける
4 用語の説明
Ⅱ 『海角七号』を観る
1 七通のラブレター
2 インペリアルな視線
3 アンチインペリアルな視線
4 ポストインペリアルな視線
5 三様の日本、三様の台湾
Ⅲ 『セデック・バレ』を観る
1 遠くて異なる世界――インペリアルな視線の弱さ
2 日本的、あまりに日本的な!――強まるインペリアルな視線
3 雄々しき益荒男ぶりの普遍性――人類学者の視線
4 樺沢重次郎は「この私」ではないか――人類学者の視線の再検討
5 モーナ・ルダオから阿弖流為へ――強まるアンチインペリアルな視線
6 アンチインペリアルな視線の揺らぎ、そしてポストインペリアルな視線へ
7 遠くて近い台湾
Ⅳ 『KANO』を観る
1 「台湾は日本の統治下にあった」という語り
2 帝国の祭典または束の間のパックス・ジャポニカ
――インペリアルな視線
3 「釘を打たれたパパイヤ」
――インペリアルな視線とアンチインペリアルな視線
4 「漢人、蕃人、日本人」という呼称への疑問――台湾研究者の視線
5 再び「釘を打たれたパパイヤ」――ポストインペリアルな視線
6 日章旗、旭日旗、そして鮮血の意味
――ポストインペリアルな視線に映る多義性
7 植民地と地方の相同性――アンチインペリアルな視線の誘惑
8 遠い甲子園、近い台湾と東北、そして曖昧な日本人
V 魏徳聖三部作が「この私」に「見せてくれた」もの
1 視線にまつわる感情の重み
2 多義的な日本、多元的な台湾、そして中国の影
3 ポストコロニアルとの対話の可能性
おわりに
参照文献・参照メディア
内容説明
植民地台湾と帝国日本。映画にこめられた歴史や民族のアヤを、戦後日本人男性という立脚点を定めて、さまざまな角度から読み解く。
*********************************************
「はじめに」より
本書は、魏徳聖三部作と呼ばれる台湾映画、『海角七号』(2008年公開)、『セデック・バレ』(2011年公開)、『KANO』(2014年公開)の描く植民地台湾と帝国日本が、「この私」にはどのように見えるかを反省する試みである。
「この私」は、戦後に日本人として生まれ育ったひとりの男性だ。「この私」は、「人類学者」として「台湾研究」をしているが、その際、知らず知らずのうちに「戦後日本人男性」という立場から台湾を眺めていて、それが「この私」の「台湾の見え方」に大きな影響を与えている。だとしたら、魏徳聖三部作の「見え方」を自己分析することで、その影響がどのようなものか明らかにできるのではないか。これが本書の問題意識である。
台湾と日本との間には長くて深い歴史的な関係があるので、台湾の人々の多くは様々な形で日本人と関わっており、日本人に対して色々な思いを抱いている。そして、その思いを我々日本人にぶつけてくる。それに、我々は戸惑う。たとえば、上水流久彦は、フィールドワークで出会った台湾人に「私も日本人だった」と言われた際、困って「応答できずにただ黙ってうなずくだけ」だったと述べている[上水流2010: 122]。台湾研究をしていると、日本人だから体験することがたくさんあるのだ。そして、日本人であれば、日本について様々な思いがあるだろう。日本人の台湾研究者は、台湾人の日本への思いと出会うたびに、自分の日本への思いと格闘しながら、台湾研究をしているはずだ。つまり、日本人であることが、日本人の台湾研究に何らかの影響を与えているに違いないのである。しかし、そのことが日本人による台湾研究の重要な要素として論じられることは、これまであまりなかったのではないか。
それならば、「この私」を例として、この問題を正面から取り上げてみよう。これが、本書執筆の動機である。日本人という立場が台湾研究に与える影響という問題を、本書では「立場性の問題」と呼ぶことにする。
魏徳聖三部作と「この私」の出会いは、とても個人的なものだった。2014年、フェイスブック上で、台湾の友人たちが『KANO』を大いに話題にし、しかもその多くが絶賛であることを、「この私」はとても奇妙に感じた。聞けば、全編ほとんど日本語で、戦前に甲子園出場を果たした嘉義農林学校の活躍を描いた映画だという。それがどうして台湾で大人気となり、しかも「この私」のフェイスブック友達のようなアカデミックな人たちまで興奮させるのだろうか。
日本公開を待って、2015年1月、仙台市内の小さな映画館で『KANO』を観た。もっと大きなスクリーンで観たくなり、数か月後、別の映画館に行った。二度の観賞を通して、いろいろな思いが去来した。そこで、日本公開版のブルーレイディスク版『KANO〜1931海の向こうの甲子園』(魏徳聖・黄志明・馬志翔2015)を購入し、自宅の52インチテレビで何度も見直した。そして、これは魏徳聖の他の作品も見なければと、まず同時代の霧社事件を描いた『セデック・バレ』(魏徳聖・呉宇森・張家振・黄志明2013)を購入し、自宅のテレビで観た。そして、最後に三部作の第一作『海角七号 君想う、国境の南』(魏徳聖2013)を、やはり自宅テレビで観た。映画の公開順とは逆に観たわけである。しかし、本書では、公開順に三作を論じることとする。
本書の焦点は、日本人という立場性が、この映画のなかで「この私」に何を見せ、何を感じさせ、何を考えさせたかにある。それゆえ、魏德聖の製作意図を問うたり、彼の三部作をポストコロニアル作品として読み解こうとしたりする意図は、本書にはない。本書における考察の対象は、「あのプロデューサー/脚本家/監督」魏徳聖が何を創り出したかではなく、あくまでも彼の映像作品が「この私」の目にどう映り、「この私」がそこから何を読み取ったかである。その考察を通して、日本人であるという立場性が「台湾の見え方」に与える影響がどのようなものかを検討する。そうすると、「この私」が男性であることや東北人であることも「この私」の立場性の重要な一部であることが明らかになってくるだろう。さらに、人類学者であることや台湾研究者であることが、「この私」の立場性をどれくらいチェックするのに役立っているかも見えてくるだろう。しかし、考察の中心は、あくまで日本人という立場性の問題である。
そのために、本書では「ポストインペリアル」という視座を提示する。なぜポストコロニアルでなくポストインペリアルなのか。そこから話を始めよう。
*********************************************
著者紹介
沼崎一郎(ぬまざき いちろう)
1982年東北大学文学部卒業。1992年ミシガン州立大学大学院人類学科博士課程にてPh.D.取得。1991年東北大学文学部講師、同助教授を経て、2004年より東北大学大学院文学研究科教授。専門は文化人類学、台湾研究、人権論、ジェンダー論(特に男性性研究)。
著書に『台湾社会の形成と変容:二元二層構造から多元多層構造へ』(東北大学出版会、2014年)、共編著に『交錯する台湾社会』(アジア経済研究所、2014年)など。


