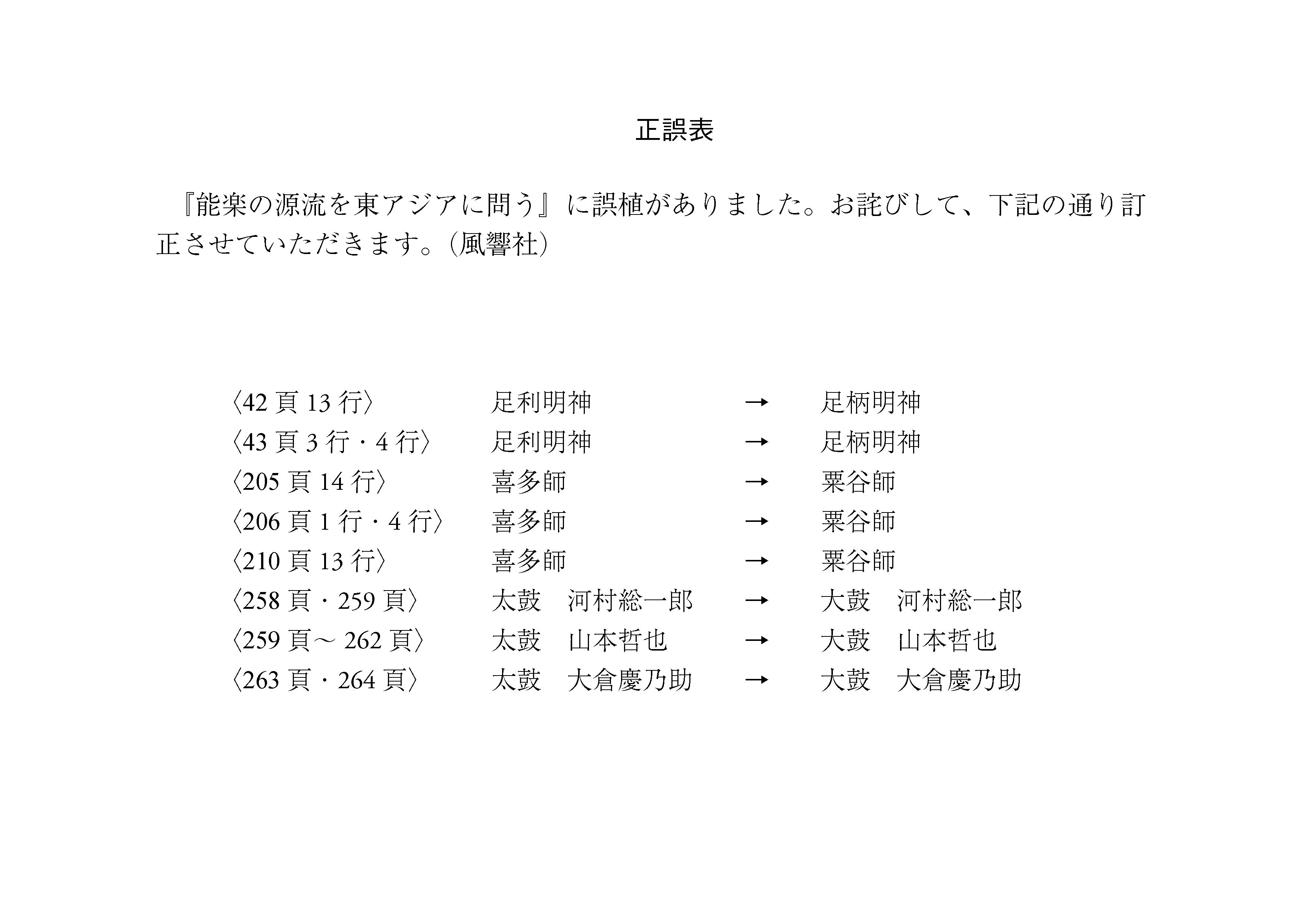能楽の源流を東アジアに問う
多田富雄『望恨歌』から世阿弥以前へ

「恨」と「幽玄」の軌跡が交わる時。その歌と舞は、東アジア芸能史千年の系譜に連なり、民衆の来し方を写す。
| 著者 | 野村 伸一 編 竹内 光浩 編 保立 道久 編 |
|---|---|
| ジャンル | 民俗・宗教・文学 歴史・考古・言語 芸能・演劇・音楽 文化遺産・観光・建築 |
| シリーズ | 風響社あじあブックス |
| 出版年月日 | 2021/12/25 |
| ISBN | 9784894893177 |
| 判型・ページ数 | A5・304ページ |
| 定価 | 本体1,800円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
目次
Ⅰ 「能」の形成と渡来民の芸能──聖徳太子信仰と観阿弥・世阿弥 (保立道久)
はじめに
一 都市芸能の原点と百済氏の没落
二 新猿楽と傀儡子の芸能
三 太子信仰と大和猿楽
おわりに
Ⅱ 中国・朝鮮・日本の仮面舞の連鎖──世阿弥まで (野村伸一)
はじめに
一 中国の仮面舞
二 朝鮮の仮面舞
三 中国、朝鮮からみた能楽の仮面舞
四 新作能および『望恨歌』への提言
Ⅲ 『望恨歌』と百済歌謡「井邑詞」 (辻 浩和)
はじめに
一 井邑詞とはどんな歌謡か
二 朝鮮における井邑詞の展開
三 日本の踏歌と井邑詞
四 望恨歌と井邑詞
おわりに
Ⅳ 強制連行に向きあった市民と『望恨歌』 (外村 大)
一 『望恨歌』が創作された時代
二 「大地の絆」と「死者への手紙」
三 市民の調査活動の展開
四 ライフヒストリーの聞き取り
五 遺族への連絡と訪問
六 歴史の継承と追悼行事
七 戦後処理の挫折と和解の模索
八 和解の原型としての『望恨歌』
Ⅴ 望恨歌・井邑詞・砧 (竹内光浩)
一 『望恨歌』に流れる三つの基調
二 『望恨歌』諸本について
三 「井邑詞」
四 能『砧』から新作能『望恨歌』へ
五 「恨」をめぐって
Ⅵ 農楽と能楽──国立能楽堂における二〇二〇年交流公演の記録 (神野知恵)
一 ことのはじまりはインドから
二 ポーランドへ渡ったチマ・チョゴリ
三 『望恨歌』公演依頼
四 清水さんとイム・ソンジュンさんの出会い
五 公演に向けての思案と準備
六 農楽隊の挑戦
七 公演当日の様子
八 二〇二一年『望恨歌』上演に向けて
『望恨歌』 (多田富雄)
多田富雄 新作能『望恨歌』公演記録(一九九三〜二〇二一) (竹内光浩/清水寛二)
解題──あとがきに代えて (野村伸一)
東アジア芸能史略年表
索引
内容説明
「恨」と「幽玄」の軌跡が交わる時
韓国の老農婦の悲痛な姿から『望恨歌』は書かれた。夫は「強制連行」により九州の炭鉱へ、そして果てたという▶本書は、この演目を歴史・民俗・文学・演者の立場から考察、「能」への新たな視点を探る▶舞台の老妻は月下でひとり舞う。その歌と舞は、東アジア芸能史千年の系譜に連なり、民衆の来し方を写す……。
*********************************************
はじめに
竹内光浩
『無明の井』『望恨歌』『一石仙人』『原爆忌』『長崎の聖母』『沖縄残月記』と問題作・話題作を世に送ってきた多田富雄さんの新作能に引きつけられた人は多いだろう。
多田さんは生命科学・免疫学の著名な研究者である。自然科学者のなかには、寺田寅彦・湯川秀樹をはじめ軽妙洒脱な随筆を書く人も多いが、多田さんのエッセイは、ご自身が小鼓を打ち、新作能を創作する経験が反映された多田さん独自のものである。
新作能とは明治以降に創作された能を一般的には指す。二百曲以上が残されているという。しかし演能回数でみると、十回以上も再演される新作能はさほど多くはない。ところが多田新作能では『無明の井』『長崎の聖母』などはすでに十回以上再演されている。国外での上演も多い。『望恨歌』も一九九三年、九五年のシテ橋岡久馬による二回の演能以来、観世栄夫が釜山公演も含めて七回、そして二〇一九年にシテ鵜澤久によって演じられた。このときは市民の手による自主的な「多田富雄の新作能を上演する会」が作られ、国立能楽堂公演が盛況裡に終えられた。
そして、二〇二一年十二月にはコロナ禍の中で「天籟能の会」主催により、『一石仙人』『長崎の聖母』『沖縄残月記』でシテを勤めてきた清水寛二師をシテとして公演される。本書は、これにあわせて公刊される。
『望恨歌』は「朝鮮人強制連行」をテーマにしたものであり、本書にもその研究者による論考が収載されている。我々は本書を「朝鮮人強制連行」だけに焦点を留めるのではなく、むしろそうした不幸な歴史を克服する道を「能楽」の源流に遡ることによって探ろうとした。
多田さんは『望恨歌』の創作において百済歌謡「井邑詞」をシテの「謡い」の詞章に採用した。
百済歌謡は亡命百済人が大きな役割を果たしていた奈良時代には都のみならず、各地の官衙で奏され、宮廷歌謡・楽舞の一つの出発点をなしたものである。東アジアの芸能はそれぞれの国が個別に作り上げたわけではなく、様々な芸能と文化、民族の交流の中で形をとってきたものである。
日本独自の芸能とみなされがちな「能」も実は東アジア文化の長く豊かな交流の中から生まれたものだった。
多田さんは二〇一〇年四月に亡くなられた。私が多田さんにお会いしたのは一度だけ、亡くなるほぼ一年前の二〇〇九年六月『沖縄残月記』本公演直前の舞台稽古の場であった。無論、発話器をお使いだった。
その記録を私が編集・執筆した『白洲次郎の沖縄・白洲正子の沖縄』(『島たや』七号二〇〇九年)に掲載した。
多田さんがNHKに委嘱されて制作された白洲正子を主人公とした新作能『花供養』の二〇〇八年初演を私は拝見したが、このときその背景にある二人の交流の深さを知ると同時に多田新作能の新たなテーマの発見を感じた。
今回の『望恨歌』公演は「天籟能の会」主催によるものである。「天籟能の会」の寺子屋方式の催しで保立道久が講師を勤めたことが本書刊行の直接のきっかけであった。その会に誘われた私は「天籟」という名称に既視感を感じていた。友人の横笛奏者鯉沼廣行が三十五年前に作曲した曲に能管独奏曲「天籟賦」(CD『天籟賦』ALMレコード)があり、私の愛奏曲のひとつでもあったからである。
「天籟」とは中国古典の『荘子』斉物論の以下の一節から来ている。
なんじは人籟を聞けども未だ地籟を聞かず。なんじは地籟を聞けども未だ天籟を聞かざらんかな
なかなか難しい物言いだが簡単に言えば、人間が演奏する音は、自然の音に及ばず、自然の音も天の音には及ばない、ということか。鯉沼もこの『荘子』の一節に惹かれて作曲したという。
演奏家にとって己の発する音よりもはるかに自然の音の方が素晴らしいことはわかっている。でも少しでもその自然の音に溶け込むように演奏したいとの想いで多くの演者は奏でている。その自然の音「地籟」を超えるものが「天籟」である。人間がいかに小さく無力なものであるかを思い知らされる『荘子』の一節である。
多田さんの新作能には、この「天籟」の笛の音が聞こえてくるように思うことがある。多田作品は臓器移植、相対性理論の延長に登場した原子力の驚異、それが現実となってしまったヒロシマ・ナガサキの原爆投下、沖縄戦、朝鮮人強制連行など現代の問題に奥深くくい込んだものが多い。つい声高に訴えたくなるようなこうした現代の悲劇をテーマにしながら、多田さんは自然科学者らしく沈着冷静に筆を進めていく。「人籟」「地籟」の先に「天籟」が聞こえるように思うのは、私だけであろうか。
さて二〇〇五年韓国釜山での『望恨歌』の公演は、「解題──あとがきにかえて」で野村伸一も述べているように、さほどの反響を呼ぶことなく終わった。そのことは成惠卿による『望恨歌』ハングル訳の解説にも書かれている。
そもそも能面をあてたシテの科白は、日本人ですら聞きとることが困難である。初演のビデオを拝見しても、手元に台本がないとかなり厳しいと感じた。おそらく会場に足を運ばれた韓国のみなさんにとっては、パントマイムを観るようなものだったのではないか。観世寿夫のパリ公演でも「オー・ノー」という感嘆とも感歎ともつかない言葉が観客から発せられたと聞く。
最近は国内での能公演でも、事前のワークショップが開催されることが増えている。今回の『望恨歌』公演でも、七回にわたってワークショップが企画された。今後、韓国だけでなく世界各地での公演にはそうした配慮が必要かもしれない。時間や会場その他でそう容易いことではないにしても……。
しかし多田富雄がこの『望恨歌』を書き、それを繰り返し公演していく中で伝えようとしたものを考える時、その努力は必須であろう。
同時に国内においても、『望恨歌』だけでなく多田富雄が現代へのレクイエムとして作り続けた『無明の井』『一石仙人』『原爆忌』『長崎の聖母』『沖縄残月記』の諸作品が、各地で再演され続けることを期待したい。
本書には専門分野を異にする六名の研究者が参加した。このような演者と研究者の共同研究は戦後の一時期盛んだったものであり、その延長上に林屋辰三郎が創設した芸能史研究会などの動きがある。私も企画編集に参加した『歴史評論』一九九六年二月号の特集「中世芸能史との対話」で林屋にインタビューをして、そのころの息吹を実感したことがある。さらにその号には、『望恨歌』の前回今回の公演に出演されているシテ方清水寛二師・笛方松田弘之師・狂言方石田幸雄師のみなさんにも寄稿いただいた。
本書の基盤になった「くまから洞芸能史研究会」でも研究者だけでなく、舞台の実演者も参加され貴重な意見を述べていただけたのはありがたいことであった。
なお、本書には、各論考冒頭に執筆者による要約を付してある。本文理解の一助としていただければ幸いである。
付載として今回の『望恨歌』公演の台本と公演記録を掲載した。台本はシテ清水寛二師補訂である。ただし、本番とは異なる部分もあることをお断りしておく。
*********************************************
執筆者紹介(掲載順)
竹内光浩(たけうち みつひろ)
1947年生。元専修大学兼任講師。日本中世史。
共編著に『天皇・天皇制を読む』(東京大学出版会、2008)。『語る藤田省三』(岩波現代文庫、2017)。
保立道久(ほたて みちひさ)
1948年生。東京大学名誉教授。日本の神話と地震・噴火史の社会史的研究。
論著に『中世の愛と従属』(平凡社、1986)、『歴史のなかの大地動乱』(岩波新書、2012)、『ブックガイドシリーズ日本史学』(人文書院、2015)、『中世の国土高権と天皇・武家』(校倉書房、2015)、『現代語訳 老子』(ちくま新書、2018)など。
野村伸一(のむら しんいち)
1949年生。慶應義塾大学名誉教授。祭祀芸能を含めた東アジア地域文化研究。
近作に編著『東アジア海域文化の生成と展開〈東方地中海〉としての理解』(風響社、2015)、「東アジアの儺──鬼神往還祭儀」ハルオ・シラネ編『東アジア文化講座 第四巻 東アジアの自然観東アジアの環境と風俗』(文学通信、2021)など。
辻 浩和(つじ ひろかず)
1982年生。川村学園女子大学准教授。日本中世芸能史。
論著に『中世の〈遊女〉──生業と身分』(京都大学学術出版会、2017)、「内教坊小考」元木泰雄編『日本中世の政治と制度』(吉川弘文館、2020)など。
外村 大(とのむら まさる)
1966年生。東京大学教授。近現代における日本と朝鮮の関係の歴史研究。
論著に『在日朝鮮人社会の歴史学的研究』(緑蔭書房、2004)、『朝鮮人強制連行』(岩波新書、2012)、「朝鮮民族にとっての一九三八年・新協劇団『春香伝』」『在日朝鮮人史研究』2018年10月など。
神野知恵(かみの ちえ)
1985年生。国立民族学博物館特任助教。博士研究では、1950〜70年代の韓国で一世を風靡した女性農楽団の演奏者に注目し、その演奏の特徴や、次世代への継承を主題とした。現在の研究テーマは、日本と韓国の専業芸能集団による門付け芸能の比較。
著書に『韓国農楽と羅錦秋──女流名人の人生と近現代農楽史』(風響社、2016)など。
多田富雄(ただ とみお)
1934年─2010年。免疫学。
著書に『免疫の意味論』(青土社1993)、『生命の意味論』(新潮社、1997)、『脳の中の能舞台』(新潮社、2001)、『寡黙なる巨人』(集英社、2007)。没後に『多田富雄新作能全集』(藤原書店、2012)。ほかに季刊『環』「特集 多田富雄の世界」(藤原書店、2010)がある。
清水寛二(しみず かんじ)
1953年生。銕仙会シテ方。東京藝術大学非常勤講師。古典曲以外にも多田富雄新作能の演出・シテを多く勤める。