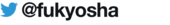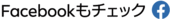目次
第一部 激動の時代を⽣き抜く──学者への道のり
はじめに
一 文革期の体験
二 文革の終息後
三 三つの専門領域との出会い
第二部 学問への道──師を語る
はじめに
一 費孝通先生
二 中根千枝先生
三 伊藤亜人先生
第三部 研究・著作の行間を語る
一 中国社会の生活実態──フィールドワークからの学び
二 中国民衆の戦争被害──記憶へのアプローチを探る
三 革命以後の政治体制──全体と個の座標軸を思索
四 日本社会に生きる──日中比較の視座を求めて
第四部 「聶莉莉」と私
本書によせて(西澤治彦)
聶先生から学んだこと(奈倉京子)
あとがきに代えて──本書の誕生まで(美麗和子)
資料編
研究の歩み/関連する主要な著述
年譜
書評・紹介・講演感想の抜粋
謝辞──執筆を終えて(聶莉莉)
内容説明
師を語り、著作の行間を語る自伝的エッセイ
「私は本書が読者に提示したのは、歴史の中に無数に存在する人間の一人としての私の足跡であると考えている。それは、革命以後の激動する中国現代史の波に翻弄されながらも、懸命に生き、学び、考え続け、時代に適応しつつも初心を大切にし、自らの原点から決して逸れることのなかった一学者の思索の記録である。微力であっても、志を抱き続けたことを誇りに思っている。」(著者・謝辞より)
*********************************************
まえがき
奈倉 京子
本書は、二〇二三年三月に聶莉莉先生が定年により大学の専任職をご退職されたことを記念し編まれたものである。退職記念論集といえば、教え子たちがこれまでのご指導への感謝を込めて自分の研究の一端を論文にして持ち寄り、編纂するのが一般的だが、私は聶先生が中国で激動の時期を生き抜き、学者になるまでの半生と、日本の学術界に身を置きながら中国社会を眼差し、目の前の現実の捉え方を思索してきた道のりを前面に出す記念論集こそが、現代の若手・中堅研究者及び一般の読者に響き、後世に残す価値のある書籍となると考えた。この考えを同窓の美麗和子さんと風響社の石井雅さんにご相談してみたところ、お二人とも賛同してくださり、とりわけ石井さんは編集者の視点から、刊行の意義を認めてくださった。
しかし、この企画を聞いた聶先生は、当初、あまり乗り気ではない様子だった。先生は、ご自身の人生は特別なものではなく、一般の読者に捧げられるものはあまりないと謙虚な姿勢を示された。私的な内容を不特定多数の読者に晒すことにも抵抗がおありだったかもしれない。恐らく、先生は教え子の厚意を無駄にしては申し訳ないという遠慮のお気持ちがあり、渋々この企画をお引き受けくださったのではないかと思う。
ところが、書き下ろしていただいた第一部、第二部、そして「行間を語る」を拝読し、これらの文章を執筆する〈覚悟〉をひしひしと感じた。過去に直面した事件・事実に対する率直な感情、それらを冷静沈着に受け止め、分析する視点、そして先生特有の文体も相まって、自然と独特の世界観に引き込まれた。
本書は、四部構成からなる。第一部は、聶先生の学者人生を貫く問題意識を形成させた激動の半生の記述である。来日以前、中国の政治動乱期の経験により、現実社会を見つめ、その中から中国社会に潜む問題の本質を摑むための方法論を先生は模索し始める。それにより、普通の人びと(個人)が全体主義国家に支配されたのはなぜか、中国農村に住む農民からみた社会の基層構造及び農民の民俗風習や世界観はどのようなものか等の問題意識が醸成されてきたことが窺える。つづく第二部では、思想的影響を受けた三人の師について語られる。目の前に現れる事実をどう捉えるかということを追究しつづけた聶先生に、三人の師がそれぞれどのような啓発を与えたかが書かれている。そして、第三部は、聶先生がこれまで従事されてきた具体的な調査研究とそれに基づく著作について紹介される。聶先生が当時どのような思索をもって調査研究に従事してきたのかを「行間を語る」でふり返る。
本書の読者層には、フィールドワークを手法として現代中国を調査研究する研究者は言うまでもなく、近現代中国史を研究する歴史学者、東アジア地域研究者、そして日本で研究者を志す留学生や異文化理解に関心があり、留学してみたいと考えている読者の方々も想定している。本書は、人類学を学ぶ若手・中堅の研究者の思考に啓発を与えるだけでなく、一般の日本の読者一人ひとりの生の営みの何かしらの部分に響くものであると思う。それは、聶先生が常に、〈取るに足らない普通の人〉の生活をつぶさに記述し、彼/彼女たちの小さな声に寄り添ってこられたからである。
本書の特徴を私なりに紹介したい。
第一に、本書は「自分のなかに歴史をよむ」ものである。唯一無二のライフストーリーとそれを基盤に醸成された中国社会に対する問題意識、そこからくる学者としての使命と責任。聶先生の著作は、どれも先生ご自身が〈私でなければできなかった〉ものである。阿部謹也は『自分のなかに歴史をよむ』(筑摩書房、二〇〇七年)の中で、学問とは自覚的に生きることであり、そのためには自分のなかを深く掘ってゆく作業が必要であるということを綴っている。研究者には対象を客観化することが求められる一方で、阿部は、対象を理解するには相手のなかに自分と同じものを見出さないと本当にわかったことにならないと言う。聶先生の著作はそのことを如実に示している。
第二に、理論や先行研究に溺れず、調査地の現場で〈事実〉に向き合う人類学の方法論が論じられている。とりわけ第二部「わが師」は、古典的な人類学的方法論の教科書として読むことができる。ここ数年、コロナ感染拡大のため、人類学を志す院生を含む研究者のなかには、現地調査ができず、理論研究に重きを置いたり、以前のフィールドデータを理論に当て嵌めて再考しようとしたりする人もいる。このような仕事を否定するつもりはないが、フィールドで本質的な問題を発見し、一次データを少しずつ抽象化し、理論的昇華をさせるという地道な手法に立ち返ることは、コロナ収束後の今だからこそ、改めて学ぶ意義があると考える。
第三に、本書には、聶先生が日本という異文化社会で学術的な訓練と生活経験を経て、祖国中国を対象化していくプロセスが記述されている。そのなかで、学者としての倫理道徳の正しさは何か、真正の学問とは何か、ということが追求されている。聶先生の、学者としての社会に対する使命感、義務感に触れると、昨今の「業績主義」を反省せずにはいられない。
第四に、本書は人間理解とは何かという人類学の命題を常に問うている。先生は常に「草の根の視点」を大切にされてきた。先生の著述には、整序立てられた冷静な論の奥に、普通の人びとの熱い生き様が垣間見える。先生は、日頃から他者を尊重することを説いてきた。ここでの他者は、近代主義的な、自立した〈あなた〉と〈私〉を二分した上で〈あなた〉の意思を尊重するというような他者でなく、「あなたの中に私がいる、わたしの中にあなたがいる」というような、異文化に生きる者同士の共通性、普遍性を見出し、理解、共感しあえる〈他者〉も内包している。
以上のように、本書に綴られたこれまでの聶先生の人生史と研究史は、聶先生の研究者としてのコアな部分を形成し、個の強さ、孤独を恐れない精神を培ってこられたのだと思う。長いものに巻かれず、妥協せず、いつもご自分の課題を追究することを中心に据えてこられた先生が、今もとても眩しい。
本書が一〇〇年後も読まれることを願ってやまない。
*********************************************
著者紹介
聶莉莉(にえ りり)
東京女子大学名誉教授
東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了 博士(学術)
専攻は、文化人類学、中国および東アジア地域研究
主著書に、『「知識分子」の思想的転換:建国初期の潘光旦、費孝通とその周囲』(風響社、2015年、単著)、『中国民衆の戦争記憶:日本軍の細菌戦による傷跡』(明石書店、2006年、単著)、『大地は生きている:中国風水の思想と実践』(てらいんく、2000年、共編著)、『劉堡:中国東北地方の宗族とその変容』(東京大学出版会、1992年、単著)など。
編者紹介
奈倉京子(なぐら きょうこ)
静岡県立大学国際関係学部教授
一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了 博士(社会学)
専攻は、文化人類学、中国および中華圏の地域研究
主著書に『中国の知的障害者とその家族:「新しい社会性」のエスノグラフィー』(東方書店、2023年、単著)、『帰国華僑:華南移民の帰還体験と文化的適応』(風響社、2012年、単著)など。
美麗和子(びれい かずこ)
東京女子大学研究員・非常勤講師
東京女子大学大学院人間科学研究科博士課程修了 博士(人間文化科学)
専攻は、文化人類学、中国地域研究およびエスニシティー研究
主要著作に、論文「建国初期の「中央民族訪問団」と中国共産党の少数民族政策」(『中国研究月報』第70巻第9号、2016年)、翻訳「貴州にいる兄弟民族:費孝通著「兄弟民族在貴州」翻訳(上)」「同(下)」(『東京女子大学紀要論集』2023-2024年)など。