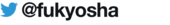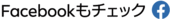目次
凡例
序論 「知と力」を生成する場
第1節 セネガル共和国概観
第2節 2つの「ポリティーク」の場を読み解く
:「公の政治(La politique )」と人々の
「日々生きるためのいとなみ(Le politique)」
第3節 仏語領アフリカにおけるイスラームの先行研究:「知(識)─(権)力」
(savoir-pouvoir)に関する認識論的再検証
●第1部 近代政治を動かした若者たち●
第1章:スーフィー教団と近代高等教育の場:知識・政治運動・人
第1節 イスラーム教育・実践の場とスーフィー教団:ダーラ、ダイラ
第2節 近代高等教育の場としての大学:植民地期から1968年の学生運動まで
第3節 サンゴール政権下における宗教・政治
第4節 初期の学生ムスリム団体と仏語話者知識人たちの
イスラームアイデンティティ (1960–1980)
第2章 アラビア語話者知識人と「改革主義」イスラーム
第1節 アラブ地域とサハラ以南のアフリカにおけるイスラーム「改革主義」運動
第2節 セネガルにおけるイスラーム「改革主義」
第3節 「対抗エリート」か「仲介者」か
:セネガルにおける二人のアラビア語話者知識人
第3章 左派思想運動の敗退と大学におけるイスラームコミュニティ
第1節 アブドゥ・ジュフ政権下の国家と社会:危機、構造調整政策、住民による
「下からのポリティーク」の狭間で
第2節 左派イデオロギーの終焉、
自由主義運動、あるいはカリスマ的宗教家の台頭
第3節 高等教育の場の変容と大学キャンパスにおける
イスラーム・アソシエーション(1980-2000)
●第2部 自由主義政権下の社会の中で
:「若者たちの導師」と新たな「ポリティーク」の場●
第4章 民主党政権下のセネガル:上からの「教団政治」と「若者たちの導師」
第1節 アブドゥライ・ワッドとセネガル民主党(PDS)の台頭
第2節 ワッド政権下のセネガル、「教団政治」とイスラーム外交
第3節 政治変革の現場に露出するイスラームの身体性
第4節 個人化する政治意識と「イスラームによる社会改革」
第5節 マッキー・サル政権から2024年の政権交代まで
第5章 「若者たちの導師」と「下からの」社会改革運動
第1節 シェーク・イブラヒマ・ニャスの信者による学生組織(DETBN)
第2節 ティジャーニー教団のカリスマ指導者、セリン・ムスタファ・シー
:信者による組織ムスタルシディーン(DMWMD)と学生信者たち
第3節 モドゥ・カラ・ンバケと「神の一体性のための世界運動」
第4節 シェーク・ベチョ・チュンと信者「チャンタコン(Thiantacones)」
第5節 「若者たちの導師」の指導者と信者たち:セネガル現代社会と
ハイブリッド化するイスラーム
第6章 イスラーム近代教育の場:教育者と学生たち
第1節 高等教育の多様化と私立のイスラーム高等教育の発展
第2節 アル=ファラフの経営するイマーム・ムハンマド・ブン・サウド校
第3節 トゥーバのアル=アズハル学院とンダム校教員、ムサの話
第4節 ピルのイスラーム・ダアワ大学
結 「改革主義」と現地のスーフィー教団文化の狭間で
第7章 宗教メディアと新たな知識・表現の場
第1節 メディアセンター・シンクタンク・シンポジウム
:教団の新たな「知―力」の創出と共有の場として
第2節 ラジオ、テレビ、ソーシャルメディア
:新たな宗教コミュニケーションの場
第3節 デジタルネイティブな信者と宗教指導者たち
●第3部 学生たちのイスラーム
:大学キャンパスにおける宗教性のエスノグラフィ●
第8章 大学キャンパスにおける宗教実践:空間と身体性のダイナミズム
第1節 大学キャンパスという空間:制度化された場所に浸透する宗教空間
第2節 キャンパス内のフレキシブルな宗教性と空間
第3節 キャンパスは聖地に繋がっている:訪問、巡礼と開かれた空間性
第4節 宗教実践とル・ポリティークの場としての身体性
第5節 キャンパスにおけるセクシャリティ、ジェンダー
:結婚ベールとジーンズの日常から
第9章 若者たちの霊性文化:もう一つの「大学」としての「道」と「修行」
第1節 魂を包む:儀礼が「身体―霊性」に作用するとき
第2節 スーフィー教団への「改宗」と修行
第3節 聖人たちのポリティークともう一つの「大学」
:秘儀領域における知と繋がり
結論 セネガル現代社会を動かす宗教性のダイナミズム
おわりに
参考文献一覧
本書関連略年表
略語一覧
写真図表一覧
索引
内容説明
現代セネガルの「ダイナミズム」を根源から探る
いまも沸々とたぎる社会、若者。その渦中に身を投じた著者は、政治や教育における変化・変革を政治人類学的手法でマクロに追いながら、学生信者たちの日常をエスノグラフィーとしてミクロに描く。アフリカの熱量とその「動的平衡」に迫る渾身の1冊。
*********************************************
はじめに
フィールド調査を通して現地で体感した、その沸き返り、むせかえるようなエネルギーの塊を、「ああ、この社会は今このとき、とてつもなく動いている!」というその実感や、その「空気」自体を、いかに捕らえ、研究対象とするのか。
本研究は、理論的な分析に加え、方法論として行き着いたエスノグラフィの形態を通して、可能な限りこうした質的な空気を「捕まえ」 (réstituer)可視化(demontrer)する試みであり、そこに自然にたち現れてくる身体性や空間のありかた、日常的な言葉の意味などを改めて文章として定着化することで理解する。これが一つの挑戦だった。
本書を読むにあたって、セネガル研究、アフリカ研究を専門分野としない読者には、第8章から読みはじめていただくのをおすすめしたい。筆者がフィールド調査を行ってきたダカール大学の情景や、セネガルの現代社会を生きる若者たちの姿について、様々なエピソードを中心に描く試みをしている。そして、彼らの生きるセネガルの社会背景についてより深い関心をもっていただけたら、1章から7章までを読み進めていただけたら良いと思う。まず、現場で見聞きし様々なことに気づいた。そして分からないこと、知らないことについては一つずつ調べ、考えた─、この読み方は、筆者自身がセネガルのフィールドと関わってきた順番と、一緒である。
社会を動かす宗教ダイナミズムをどう理解しどう描くか? これが本書を通じた大きな問いである。筆者は、教育の場であると同時に常に政治の場となってきた大学や高等教育機関における様々なイスラームの動き─中でもセネガルに複数存在するスーフィー教団やその下集団、そしてアラブ思想に影響を受けたと言われる改革主義系の運動等─に着目し研究対象とすることで、近現代におけるセネガル社会の大きな変化を描きだすことができるのではないかと考えた。また、政治的社会的に大きな役割を担ってきた宗教的な学びの場や、イスラームのコミュニティが運営する『フランコ・アラブ』と呼ばれる近代教育機関、宗教大学においても調査を行った。本書はこうした調査を通し、セネガルの教育と政治の場を形成してきた様々なイスラームの動きとその中にいる「ひと」について明らかにし、現代を生きる若い信者たちの信仰生活を描きだすことで、現在進行形でセネガル社会を変化させていく宗教性のダイナミズムを理解することを試みている。
筆者が初めてセネガルを訪れたのは2003年、大学2年生の夏だった。ダカール・ヨフ地区の旧空港に旅客機が降り立っていたころで、鉄筋の階段の手すりを頼りに飛行機からシャトルへ向けて降りていく長身の人々に続き、初めて降り立ったアフリカの温かく塩臭い空気を吸い込みながら、懐かしく新鮮な、不思議な感覚に襲われたのを今も鮮明に覚えている。海にせり出した半島に位置するアフリカ大陸最西端の首都ダカールは、かつて植民者たちが新たな拠点として見出したレブーと呼ばれる漁民の暮らす小さな村から、西アフリカを代表する大都市に発展した。
現地の家庭にホームステイしながらはじめて滞在したダカールと、そこで生きるスーフィー教団の信者たちの持つ計り知れないエネルギーに魅せられ、翌年2004年から、当時約3万5000人、今や倍以上の8万人を超える学生をかかえるセネガル最大の国公立大学、シェーク・アンタ・ジョップ大学(Université Cheikh Anta Diop、以下ダカール大学)への留学を決めた。同大学の友人たち、そしてダカールの街で生きる若い信者たちと生活や信仰実践を供にしていく中で、政治・経済や社会と深く結びつきながら、「ムリッド教団」という特徴的なスーフィー教団で知られ、「寛容・穏健」と言われるセネガルのムスリムの人々と、イスラーム社会を理解したいと考えた。
その後セネガルで修士課程を終え、2009年よりフランスに留学することになる。文献調査で立ち寄ったパリで、セネガルや西アフリカに関する研究の多大な蓄積について知ったことがきっかけだった。元宗主国であるフランスの国立図書館に西アフリカ仏語圏に関する文献資料が豊富であることには何ら不思議はないが、その中でも特にセネガル、そしてムリッド教団に関する文献の多さは特筆すべきものだった。
なぜセネガル研究、ムリッド研究が当時のフランスの人類学やアフリカ研究においてこれほどまで「流行した」のか。これにはフランスの行った植民地化のプロジェクトにとって、今のセネガルに当たる地域が重要な役割を果たしてきた場所だったということに加え、特に1980年代から1990年代、それまでの人類学や民族学中心だったアフリカ研究が「開発学」や「途上国研究」という文脈に置き変わる時代に、セネガルのムリッド教団がフランスのマルクス主義社会学者や、少なくともそうした思想的傾向にシンパシーを持つ研究者たちに格好の事例研究であったことが大きく関わっている。このことについては、序論と第1章にて取り扱うが、パリに到着したばかりで右も左も分からなかった筆者は、当時のセネガル研究を代表するジャン・コパンス(Jean Copans)など、何人かの研究者の元を訪れ指導を乞うことにした。
白いあごひげを蓄えたコパンスは、当時既に高齢だったが、Politique Africaine誌を含む多々の研究誌の査読者としても精力的に貢献し、若手研究者の育成に力を注いでいた。当時既に退職寸前で博士課程の学生はもうとらないと決めていたコパンスからのアドバイスをうけ、西アフリカ研究を専門とするフランス人人類学者、ジャン=ピエール・ドゾン(Jean-Pierre Dozon)に師事することになり、所属先の社会科学高等研究院(EHESS)で研究員の仕事をしたり、同大学院の講義を担当しながら、10年ほどかけて2019年に本書の元になった博士論文、「セネガルの高等教育の場におけるイスラームのダイナミズム(Les dynamiques de l’islam dans les lieux de l’enseignement supérieur au Sénégal)」を発表した。
本書は上記の博士論文を元にしつつ、日本の読者のために仏語論文では割愛した前提知識や文献資料についての補足を加え、筆者のより近年の研究成果についても加筆して、大幅に再編集したものである。
*********************************************
著者紹介
阿毛 香絵(あもう かえ)
1983 年生まれ。
2019年フランス国立社会科学高等研究院(セネガル国立サン・ルイ大学ダブルデグリー)社会人類学・民族学博士課程修了。博士(民族学・社会人類学)。
専門分野は文化人類学、アフリカ地域研究。
現在、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科助教。
主著書として、阿毛香絵・樫尾直樹「現代社会における宗教性に関するアフリカ・アジア比較研究の可能性:認識論的視座の再検討」(『京都精華大学紀要』第57号、2024年)、Kenichi Sawazaki, Kae Amo, Yo Nonaka, Shuta Shinmyo, Mamoru Hasegawa, Ahmed Alian, Yunus Ertuğrul, “Emergent Use of Visual Media in Young Muslim Studies(ヤング・ムスリム研究における映像メディアの新たな利用)” (TRAJECTORIA, Anthropology, Museums and Art, Museums and Art, Vol.5, National Museum of Ethnology〈国立民族学博物館〉、2024年)など。