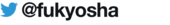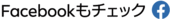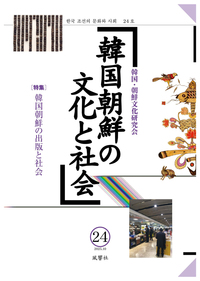
出版が社会をどう変えたのか、近代以前から現代に至る両者の関わりとその文化的な意義に焦点を当てた論考と一般論文、書評など。
| 著者 | 韓国・朝鮮文化研究会 編 |
|---|---|
| ジャンル | 定期刊行物 |
| シリーズ | 雑誌 > 韓国朝鮮の文化と社会 |
| 出版年月日 | 2025/10/15 |
| ISBN | 9784894899742 |
| 判型・ページ数 | A5・258ページ |
| 定価 | 本体3,500円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
目次
特集「韓国朝鮮の出版と社会」について 中尾道子
★特集論文
総合雑誌『開闢』(一九二〇〜一九二六年)と読者
――植民地期朝鮮における出版大衆化に関する一考察 田中美佳
★一般論文
現代韓国における村落祭祀の継承
――地方文化財指定を契機とした担い手/担い方の変容を中心に 重岡こなつ
集団買春観光の発明
――一九七〇年代初頭の日本と韓国間のキーセン観光を中心に 森田智惠
戦後京都の朝鮮人教育運動のミッシングリンクをつなぐ
――兪仁浩(一九二九~九二)の留学生時代の日記をもとに 板垣竜太
★研究ノート
台韓日の境界人・任将達の越境的音楽人生と水晶レコード 山内文登
★展評
「『死を肖像する』鄭梨愛×金セッピョル 文化人類学とアートの協働がひらく地平」展 松岡とも子
★書評と応答
影本剛『近代朝鮮文学と民衆――三・一運動、プロレタリア、移民、動員』 藤井豪
古田富建著『恨の誕生──李御寧、ナショナルアイデンティティー、植民地主義』 新里喜宣
★ひろば/マダン
京城時代の安倍能成を知るために 通堂あゆみ
共同体と父母の役割 本田 洋
★エッセイ
蔚山の長生浦クジラ博物館を訪ねて 辻 大和
★彙報
編集後記
英文目次・ハングル目次
韓国・朝鮮文化研究会会則
執筆者一覧
内容説明
*******************************
特集「韓国朝鮮の出版と社会」について 中尾道子 より
一 大会シンポジウムの趣旨──なぜ「出版と社会」を問うのか
韓国朝鮮社会は、金属活・木活字印刷や木版による印刷などに代表されるように、古来、高度な印刷・文字文化を発達させてきた。本研究会においては過去の研究大会で関連するテーマで二回シンポジウムを行っている。二〇〇六年の第七回研究大会では「文字と無文字のあいだ」というタイトルで、文字のもつ文化的・社会的な意味について検討され、二〇一五年の第一六回研究大会では「韓国朝鮮社会と記録/記憶の諸相」というテーマで、韓国朝鮮のとくに伝統社会において、人々が日々の営みや思いをどのような手段・方法によって記録し、記憶してきたのか、その特徴について議論がなされた。第二五回研究大会のシンポジウムでは、この過去二回のシンポジウムにおける問題意識を念頭に置きつつも、やや視点をずらし、(メディアとしての)出版が社会をどう変えたのか、出版と社会の関わりについて、近代以前から現代に至るまでの歴史とその文化的な意義に焦点を当てることにした。出版文化の隆盛は、情報の伝達やルート、知識の形成、文学・思想の発展にさまざまな影響を与え、政治・社会の動きとも深く関わってきた。それゆえ出版に関する研究は、書誌学などの分野のみならず、文学・思想を含む文化全般、さらには社会を理解するうえにおいても有用な切り口となる。
出版とは、ごく一般的に理解されるところによれば、「文書・図面を印刷してこれを発売・頒布すること」であるが、韓国朝鮮の伝統社会では、印刷された本(版本)と人の手によって書き写された本(写本)が流布し、読まれ書写されてきた。韓国朝鮮では早くに印刷技術が発達し、その長い歴史において出版文化の花を咲かせてきたが、一九世紀に民間による営利を目的とした商業出版がさかんとなってもなお写本の比重は高く、二〇世紀以前までは印刷によらない手書きの本が多く出回り、流布していた。世界最初の金属活字による印刷は、文化史的に大きな価値をもつものであるが、一方で、金属活字による印刷が書物の大量生産に直結しなかった点にも留意する必要がある[吉田 二〇一一]。どのような方式、形態で出版するかは、文化的な問題だけではなく、当時の社会の書物に対する需要とも密接に関わっているということである。
韓国朝鮮において活版印刷による近代的な出版物が登場するようになるのは一八八〇年代のことである。植民地期における民族運動や文芸活動は、世界の最先端の知識や思想を摂取し、それを民衆に拡散することで展開していったが、その際、新聞や雑誌、書籍といった出版物が情報の伝達や普及に大きな役割を果たした[田中 二〇二二]。
さらに「出版」は、今日の韓国朝鮮社会における知のあり方を考察するうえでも意義を有する。二〇世紀末から続くデジタル技術の発達により、IT強国である韓国ではいち早く電子化が進み、情報技術、社会制度とも連動しながら出版メディアとその読書空間も変容を迫られている。これまで自明であった冊子体の存在が相対化されつつあり、出版をめぐる環境は劇的な変化の局面を迎えている。
今回のシンポジウムは、出版を対象として取り扱ったものの、あらかじめ「出版」という語の指示対象を固定してしまうことはせずに、その変容に焦点をあてるとともに、出版が社会における知の伝達・形成・蓄積といかに連動しているのかを問うものであった。文学・歴史学・社会学などさまざまな角度から韓国朝鮮の出版文化の諸相について具体的な分析を行い、出版が社会においてどのような位置付けにあるのか、さらには韓国朝鮮社会における知のあり方にどのような変容をもたらしたかについて、出版という事象を通して文化的視点の共有を広げ、議論を深める場としたいというのがそもそもの趣旨である。従来もこうした視点からの研究がなかったわけではないが、多くは個別的な研究にとどまっているように思われるため、出版を社会における文化事象としてとらえ、総合的に究明できないかと考えた次第である。韓国朝鮮社会の出版の動態を明らかにしていくことによって、そこに記された内容を研究資料として用いるということのみならず、それが人びとの間でどのように扱われ、知のあり方にどのような影響をもたらしたのかについて検討し、過去から現在に至るまでそれらを生み出して継承する当該地域の社会を考えるというのが本シンポジウムの目的であった。
二 本シンポジウムの内容と今後の展望
本号の特集「韓国朝鮮の出版と社会」は以上のような趣旨のもと、二〇二四年一〇月二六日に帝塚山学院大学を会場として開催された韓国・朝鮮文化研究会第二五回研究大会における同名のシンポジウムの成果である。諸般の事情により、今号では報告者全員の寄稿・掲載はかなわなかったが、その代わりに、ここではシンポジウムの内容を簡単に紹介しておきたい。
韓国朝鮮では早くから木版印刷が行われ、金属活字印刷では世界に冠たる歴史をもつが、坊刻本、すなわち民間の営利出版、商業出版の出現は遅く、一八〇〇年頃以降とされている[이윤석 二〇一六]。山田恭子氏の報告「韓国古典の印刷と流通」では、印刷出版文化の始まりと近代以前における展開およびその流通が概観され、日本における韓国古典籍の収集について、とくに二〇世紀以降の状況が整理して論じられた。日本で収集された韓国古典籍のほとんどが漢籍であったこと、また、一九世紀以降、朝鮮ではハングル小説が刊行され、書籍の大衆化が促されたものの、本格的な流通は二〇世紀以降であることが指摘され、その要因として、朱子学の基本理念が背景にあり、娯楽としてのテクストが発展する余地が極めて少なかったことが挙げられた。
田中美佳氏の「総合雑誌『開闢』(一九二〇~一九二六年)と読者──朝鮮における出版「大衆化」の一断面」は、一九二〇年代を代表する総合雑誌であった『開闢』の文芸欄の変遷を分析することを通し、植民地期朝鮮における出版界の「大衆化」に迫ろうとするものである。とくに、文芸欄の占める割合や性格の変化を、読者の同誌に対する要望やそれに対する編集側の対応に注目しながら考察がなされた。その結果、編集側が読者の声を一部では受け入れつつも、『開闢』の目指す方向性に合わせて誌面を構成する際に、日本の出版物を活用していた点にも言及されている。田中美佳氏の報告については、当日の議論を踏まえて加筆修正がなされた論文「総合雑誌『開闢』(一九二〇~一九二六年)と読者──植民地期朝鮮における出版大衆化に関する一考察」が本号に掲載されているため、詳細はそちらをご覧いただきたい。
森類臣氏の報告「現代韓国における「出版」の役割とその変容──ジャーナリズム論からの検討を中心に」では、(マス)メディアを空間として展開される言説の内容とその思想性を研究する「ジャーナリズム論」に立脚し、権力・公共圏・社会運動などの要素を踏まえながら一九四八年以降の韓国のジャーナリズムを分析してきた立場から二2つの問題提起がなされた。まず、一九四八年以降の出版界(主に新聞・雑誌)における重要なメディア/事件にはどのようなものがあり、それが持つ意味は何かという問いである。次に、一九四八年以降に出版刊行物が担ってきた役割と、公共圏がインターネット上に移行し、さらに多様なWEBメディアの出現によって新聞・雑誌・放送の境界が曖昧になりつつある今日の韓国社会における、「出版(출판、publishing)」の状況と領域(およびその再検討)の問題が取り上げられた。WEBメディアの標準化は、出版(新聞・雑誌・書籍・漫画など)と放送コンテンツ・映像コンテンツなどの境界に急激な「溶解」をもたらしており、ユーザーにとっては伝統メディアの区分を「越境」することが今や当然となっており、このような状況は、ジャーナリズムのみならず「出版」概念自体にも大きな変化をもたらしていることが示された。今回は残念ながら寄稿いただけなかったが、『韓国ジャーナリズムと言論民主化運動──「ハンギョレ新聞」をめぐる歴史社会学』[森 二〇一九]その他にすでに発表された論考を参照されたい。
「出版」というテーマは、何が出版か、何を出版とするかというところから出発して幅広い接近がなされる分野である。今回のシンポジウムでも出席者はもちろん報告者全員が必ずしも同じ問題意識に立脚していたわけではないが、いずれの報告においても、「出版」が誰に向けてなされるのか、すなわち「大衆化」や「公共圏」といったその時代における社会との関わりが取り上げられたことは、今後、継続してこのテーマを考えていく上で示唆に富むものであった。また、総合討論では、「出版」とは何かという議論の中で、族譜や地図、辞典といった「読まない本」の存在、すなわち、「出版」が必ずしも「読書」とは結び付かないという指摘もなされた。あわせてコンテンツの権威性と媒体(の権威性)との連関にも話題が及んだ。「出版」というテーマは時代を超えてさまざまな切り口からの接近を可能とする問題であり、また、韓国朝鮮研究のみならず、他地域・他分野の研究者にとっても刺激的なテーマである。まだ論ずべきことは数多く残されており、本号の特集ではそのごく一部について取り扱っているに過ぎない。今大会を契機に、これから様々な議論がなされることを期待したい。
(後略)
*******************************
執筆者一覧(掲載順)中尾 道子 東京大学大学院人文社会系研究科 研究員
田中 美佳 鹿児島国際大学国際文化学部 講師
重岡こなつ 東京大学大学院人文社会系研究科 博士課程
森田 智惠 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 博士後期課程
板垣 竜太 同志社大学社会学部 教授
山内 文登 国立台湾大学文学院音楽学研究所 教授
松岡とも子 国立民族学博物館 外来研究員
藤井 豪 東京外国語大学大学院総合国際学研究院 准教授
影本 剛 立命館大学ほか 非常勤講師
新里 喜宣 福岡大学人文学部 准教授
古田 富建 帝塚山学院大学リベラルーツ学部 教授
通堂あゆみ 武蔵高等学校中学校 教諭、九州大学韓国研究センター 学術共同研究員
本田 洋 東京大学大学院人文社会系研究科 教授
辻 大和 東京大学東洋文化研究所 准教授