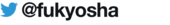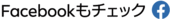孔子や光源氏が弾いたという古楽器は、長く中国と日本をつなぐ存在だった。謎の楽器・古琴(こきん)をひもとく概説書。
| 著者 | 栂尾 亮子 著 田中 有紀 著 |
|---|---|
| ジャンル | 芸能・演劇・音楽 |
| シリーズ | ブックレット《アジアを学ぼう》 > ブックレット〈アジアを学ぼう〉別巻 |
| 出版年月日 | 2025/10/15 |
| ISBN | 9784894890558 |
| 判型・ページ数 | A5・78ページ |
| 定価 | 本体800円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
目次
一 古琴について(栂尾亮子)
1 古琴の紹介
2 楽器としての側面
3 古琴の物語
4 名曲
二 中国音楽史における古琴(田中有紀)
1 図書目録における音楽と八音のなかの古琴
2 技巧と道徳性の間で
3 嵆康の琴論
4 詩と音楽
三 日本での受容(栂尾亮子)
四 琴楽の美と技をめぐって(栂尾亮子)
1 何が重視されているのか
2 変化に寛容な側面
五 教養としての古琴(田中有紀)
1 現代中国における古琴の教習
2 現代日本における古琴の教習
3 いま古琴という楽器に出会うということ
おわりに(栂尾亮子)
注・主要参考文献
琴(古琴)関連略年表
内容説明
古琴ってなんだろう?!
孔子や光源氏が弾いていたというから、文字通り古くからある琴だけど、現在よく見る琴とは形も音色も弾き方もちょっと違う。小さいけれど、長い歴史をもち中国と日本をつなぐ存在でもあった。本書はそんな謎の楽器をひもといてくれる珍しい解説書。どうぞご覧あれ……。
*********************************************
はじめに(栂尾・田中)より
本書は琴人・栂尾亮子と、中国思想研究者・田中有紀の両名による、古琴という楽器に関する小さな本である。
音楽専攻の栂尾は、中国留学中に現地の大学で、古琴という楽器が中国音楽史に有する存在感を知った。ある日、先輩の留学生が宿舎で練習する古琴の音色を近くで聴いていると、その場がはるか昔に遡った感覚に襲われた。自分でも習い始めるが、どの琴曲に接しても漠然としてよく理解できない。古琴演奏の録音には、キュルキュルという摩擦音が頻出する。また、実際に生演奏を聴きに行ってみると、楽音は聴こえないのに、奏者が左手をまだ動かし続けている。なぜそんな弾き方をするのだろう、この演奏の背景には、どんな考え方があるのだろうか。帰国後もその疑問に導かれ、答えを追い続けながら、古琴への理解を少しずつ深め、演奏を続けているうちに今に至る。
かたや中国思想を専攻していた田中も中国留学が契機となり、儒学の中の音律学に注目することとなった。帰国後、儒者が書いた文章の中で、古琴の弾き方を知らなければどうしても読めない箇所にぶつかり、古琴教室の門をたたいた。古琴を取り寄せ、毎日弾くぞと決意を固めたものの、日々大学の仕事に追われて大した練習もできない。それでも、中国の文人たちが肌身離さず大切にしていたという古琴を、自分自身が実践しなければ、彼らの思想なんてわからないだろうと思い、自分のペースで練習を続けている日々である。
このように私たちは、それぞれ異なる仕方で古琴という楽器にかかわってきた。始めは琴楽(古琴音楽)を理解できず戸惑い、溢れる疑問に導かれ続けた栂尾と、中国音楽の思想を理解するために古琴に出会った田中とでは、同じ楽器に惹かれていても、古琴を通して見ようとしている世界は全く異なるのかもしれない。本書はこのような私たち二人が、時には意見を戦わせつつも、古琴という楽器の面白さ、音色の美しさをもっと伝えたいという思いで、共に執筆した本である。
古琴の持つ意義や面白さについて、まず二点挙げておきたい。ひとつは、古琴を通じた古典芸術の理想への探求が意識されている点であり、それは東アジアをはじめとしてシンガポール、マレーシアでも現在進行形である。もうひとつは日本と中国の間で、古琴をめぐる人・楽器・楽譜の交流が、断続的ではあるが続いている点である。中国発祥の古琴への理解を通して、単に中国の伝統文化に触れるだけでなく、古琴とその音楽が現代の私たちにとっても意味があり、さらには日中の音楽文化交流を知る手がかりでもあると伝えたいと考えている。
今なぜ古琴をとりあげるのだろうか。奈良時代には唐から伝来していたと考えられている古琴は、音楽史や文化史から見ても日本と重要な交流を示す楽器であるにもかかわらず、音量が小さく地味なためか、今日の日本ではあまり知られていない。情報発信が容易になっても、ネット上の古琴の情報や動画は質の面で玉石混交の感がある。今世紀初め、古琴の演奏技がユネスコの無形文化遺産に登録されたのを機に中国では注目を集め入門書から専門書まで選択肢が広がったが、日本語で書かれたものは少ない。そこで本書は、古琴に興味を持ち、始めようとする人たちにとって、読みやすくかつ近年の学術を反映した書籍として、身近に置いてもらえるような存在になりたいと考えている。漢字ばかりで馴染みのない用語も多いが、興味のあるところから読んでいただくとよいと思う。
古琴についての基本事項や音楽的特徴については栂尾が、その背景となる思想文化と現代中国および日本における琴楽の意義については田中が担当し、次の構成で述べていく。第一節は古琴についての導入と名曲の紹介である(栂尾)。第二節は中国音楽史における古琴について論じる(田中)。第三節は日本での受容を概観する(栂尾)。第四節は担い手の考え方を中心に、琴楽の特徴を鑑賞や演奏の側面から論じる。古琴の場合、奏者が研究者でもある場合が少なくない。ここでは当事者が使う用語「声韻」(声は旋律を構成する基幹音で、そこから派生し変化するのが韻。二者は骨と肉の関係に比される)、書法(文字の書き方)等を切り口として、何が重視されているのかについて補足しつつ紹介する。さらに古琴の記譜法の特性・演奏解釈(打譜)、演奏の改変に対する奏者の姿勢に着目し、変化に寛容な古琴実践のあり方について述べる。第五節では近年、教養のひとつとして盛り上がる琴楽に光を当て(田中)、第1項では現代中国の事例を、第2項では現代日本の事例を取り上げる。そして第3項では、いま私たちが古琴という楽器に出会い、その技術を学ぼうとすることが、いかなる意味を有しているのか、本書で述べたことをふまえながら考察する。
欲張りかもしれないが、本書が古琴を通して読者の芸術観や音楽体験を豊かにする一助になり、あるいは国際理解につながるきっかけとなったら幸いである。
なお、本文の記述に際し訳文は既訳があるものはそれを参照したが、一部を変更した場合もある。それ以外は筆者による訳である。
(後略)
*********************************************
著者紹介
栂尾亮子(とがお りょうこ)
1968年、東京生まれ。お茶の水女子大学博士後期課程単位取得退学。音楽学専攻。2004年から2007年に、松下国際スカラシップにより、中国音楽学院音楽学系(北京)に留学。古琴の魅力を伝える活動をマイペースで続けている。翻訳資料に「『谿山琴況』日本語訳(上)」『お茶の水音楽論集』18号、「『谿山琴況』日本語訳(下)」『お茶の水音楽論集』21号がある。
田中有紀(たなか ゆうき)
1982年、千葉県生まれ。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。立正大学経済学部専任講師、准教授を経て、現在、東京大学東洋文化研究所准教授。専門は中国思想史、中国の科学と音楽の思想。2008年より2010年まで、松下国際スカラシップにより、北京大学哲学系に留学。
著書に『中国の音楽思想――朱載堉と十二平均律』(東京大学出版会、松下正治記念学術賞・田邉尚雄賞受賞)、 主要論文に「士大夫の音楽論における北宋の経験:鐘の鋳造と『宣和博古図』の古器蒐集」(『宋元明士大夫と文化変容』)などがある。