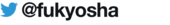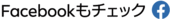中国の人類学を読む
自選書評集=一九八〇〜二〇二〇年
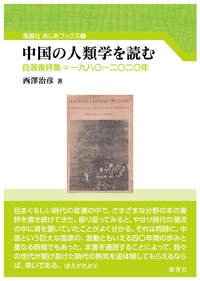
中国に住む人びとの暮らし、生き様、価値観とは何か。あたかも定点観測のごとく見つめてきた営為は、そのまま文化批評の作品である。
| 著者 | 西澤 治彦 著 |
|---|---|
| ジャンル | 人類学 民俗・宗教・文学 |
| シリーズ | 風響社あじあブックス |
| 出版年月日 | 2025/09/30 |
| ISBN | 9784894893153 |
| 判型・ページ数 | A5・312ページ |
| 定価 | 本体2,200円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
目次
凡例
●食事文化
英語圏における最初の中国料理史の概説書
──Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspectives
米国における中国食物史研究の動向
──Food in Chinese Cultureの評価をめぐって
料理の比較社会学
── Cooking, Cuisine and Class: A Comparative Sociology
東アジアのマクドナルド
──『マクドナルドはグローバルか』をめぐって
ヒトは料理で進化した?
──『火の賜物』をめぐって
食文化論としての『甘さと権力』
──シドニー・ミンツの古典を読む
越境する「中国料理」の詳細な跡付け
──『中国料理と近現代日本 食と嗜好の文化交流史』
●人類学
革命後の中国における老人扶養
──Long Lives: Chinese Elderly and the Communist Revolution
上海の蘇北人
──Creating Chinese Ethnicity: Subei People in Shanghai 1850-1980
中国本土における風水研究の幕開けを告げる書
──『風水の社会人類学 中国とその周辺』
一人の中国人人類学者の軌跡を通して見る現代中国の歩み
──『大地の民に学ぶ 激動する故郷、中国』
中国人類学の古典を読む
──『生育制度 中国の家族と社会』
●民族誌
モシャー事件の副産物
──Broken Earth: The Rural Chinese
中国農村社会における宗族と政治
──Chen Villageをめぐって
人類学者による歴史人類学の試み
──『中国人の村落と宗族 香港新界農村の社会人類学的研究』
中国農村社会研究の新しい展開
──『劉堡 中国東北地方の宗族とその変容』
人類学者による客家像の再検討
──『客家 華南漢民族のエスニシティーとその境界』
中国民族誌の新たな試み
──『中国湖北農村の家族・宗族・婚姻』
中国における「民族」研究のさらなる展開
──『民族生成の歴史人類学 満州・旗人・満族』
●民俗・文芸史・東西交流史
民国期の北京市民生活の小百科全書
──『北京風俗大全 城壁と胡同の市民生活誌』
文芸史の側面から農村と都市を繫ぐ試み
──『中国近世文芸論 農村祭祀から都市芸能へ』
イギリス人宣教師の見た清末の中国社会
──『清国作法指南 外国人のための中国生活案内』
マルコ・ポーロ『東方見聞録』新訳の意義
──『マルコ・ポーロ東方見聞録』
●文学作品
中国農村社会の息吹を伝える
──『古井戸』
したたかな農民の姿描く
──『中国の村から 莫言短編集』
声無き死者への鎮魂歌
──『神樹』
●文化大革命・中国革命
蓄積されていく文革の証言(1)
──『上海の長い夜』『庶民が語る中国文化大革命』
蓄積されていく文革の証言(2)紅衛兵編
──『ビートルズを知らなかった紅衛兵』『私の紅衛兵時代』『ある紅衛兵の告白』
蓄積されていく文革の証言(3)通史のなかの文革
──『ワイルド・スワン』
中国革命研究への新たな視座
──『革命の実践と表象 現代中国への人類学的アプローチ』
知識人の思想的転換を通してみる中国革命の光と影
──『「知識分子」の思想的転換 建国初期の潘光旦、費孝通とその周囲』
あとがき
書評に関連する年譜
初出一覧(ジャンル別 掲載順)
内容説明
激動の40年を書評でたどる
中国を主題とする人類学や歴史・文学の名著31冊──その鋭い分析や洞察、幅広い主題は、本書によって俯瞰され、エッセンシャルに再提示される。すなわち、中国に住む人びとの暮らし、生き様、価値観とは何か。あたかも定点観測のごとく見つめてきた営為は、そのまま文化批評の作品である。
*********************************************
まえがき
本書は、私がこれまでに書いてきた書評を集めたものである。最初に書いた書評が、K・C・チャン編のFood in Chinese Cultureであった。まだ大学院生の時であった。その後、食事文化関係にとどまらず、中国人類学や民族誌、民俗や文芸論、現代文学や中国社会論などの分野における学術書や一般書の書評を書いてきた。
書評を収録するにあたっては、新聞の書評欄に書いた短い新刊紹介も二本、含めることにした。また読者の便を考えて、いくつかのジャンルに分けたが、その中では書いた順番に並べている。項目別ではあるが、順を追って読み進めれば、私が書いてきた書評、言い換えれば、刊行され、読んできた本の展開が追えるようにもなっている。
ジャンル別の書評の数は、食事文化関係が七本、人類学が五本、民族誌が七本、民俗・文芸史・東西交流史が四本、文学作品が三本、中国革命関連が五本となり、これらを合計すると三一本、書評した本の数で言うと、三三冊になる。
三三冊というのは書評家からみれば少ないし、書評に取り上げられるべき本は他にもたくさんある。しかし、私は書評家としてこれらの書評を書いてきたわけではなく、本を読んで、書評を書きたいと思った本だけを選んできた結果である。新聞に掲載された新刊紹介だけは、依頼されたものであるが、それでも面白い本と思わなければ引き受けることはなかった。書評している本の多くは専門書であり、本書は、一般の読書人に向けた中国関係の本の紹介というよりは、書評論文的な文章を集めたものとなっている。
本の選択は私個人によるものであるが、時代別に並べてみると、過去四〇年間の人類学をはじめとする中国研究の流れも概観できることに気づいた。そこで、巻末に、初出一覧のほか、年譜をつけた。書評を書いてきた本の出版を、当時の時代背景や研究者としての私個人の歩みの中に位置づけてみるのも、一興かなと思ったからである。
年譜に整理してみると、日中国交正常化が一九七二年のことで、私が大学院に入学する前年の一九七八年に、中国が改革開放路線に大きく舵を切った「三中全会」が開かれている。このおかげで、それから七年後の一九八五年に、中国政府の奨学金(七九年の第一期生から数えて六期目)を得て南京大学に留学することができた。中華人民共和国が建国されてまだ三五年目のことであった。帰国後の一九八九年四月に武蔵大学に職を得たが、その年の六月に天安門事件という衝撃的なことが起った。
一九九〇年代以降は、書いてきた書評を振り返ると、文化大革命や中国革命を検証するような著作が多く出版されたことが一目瞭然となる。また、中国人留学生を含め、若手の人類学者らによる民族誌も陸続と出版されるようにもなってきた。一九九七年七月の香港返還も忘れ得ぬ出来事であったが、それから僅か二三年にして「一国二制度」が崩壊するとは、その時、誰が予想しただろうか。
二一世紀に入ると、中国は驚異的な経済発展を遂げていくが、それはさまざまな負の遺産を背負っての離陸でもあった。二〇〇八年には、四川大地震と北京オリンピックという対照的な出来事が起こった。また、二〇二〇年の新型コロナウイルスの発生は、二〇〇二年のSARSの衝撃を遙かに超えるものであり、その影響は全世界に及び、我々はまだその渦中にある。これも一体、誰が予想できたであろうか。
こうした目まぐるしい時代の変遷の中でも、中国人類学や食文化をはじめとして、さまざまな分野の本の書評を書き続けてきた。こうして振り返ってみると、自らの意思で読む本を選び、書評を書いてきたとはいえ、やはり時代の潮流の中に身を置いていたことがよく分かる。それは同時に、中国という巨大な国家の、激動ともいえる四〇年間の歩みと重なる時間でもあった。本書を通読することによって、我々の世代が駆け抜けた時代の熱気を追体験してもらえるならば、幸いである。
*********************************************
著者紹介(掲載順)
西澤治彦(にしざわ はるひこ)
1954年広島県生まれ。筑波大学大学院人文社会科学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学・総合研究大学院大学)。武蔵大学人文学部教授を経て、2021年より武蔵大学名誉教授。
著書に『中国食事文化の研究――食をめぐる家族と社会の歴史人類学』(風響社 2009)、『中国映画の文化人類学』(風響社 1999)、編著に『「国民料理」の形成』(ドメス出版 2019)、共編著に『フィールドワーク――中国という現場、人類学という実践』(風響社 2017)、『中国文化人類学リーディングス』(風響社 2006)、『大地は生きている――中国風水の思想と実践』(てらいんく 2000)、『アジア読本・中国』(河出書房新社 1995)、訳書に費孝通著『郷土中国』(風響社 2019)、共訳書に費孝通等著『中華民族の多元一体構造』(風響社2008)、フリードマン著『東南中国の宗族組織』
(弘文堂 1991)など。